本文
壬申の乱時代背景
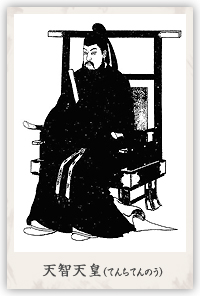
中大兄(なかのおおえ)皇子(のちの天智天皇)は、中臣鎌足(なかとみのかまたり)らと謀り、乙巳(いっし)の変といわれるクーデターを起こしました。中大兄皇子は、母である皇極天皇からの譲位を辞退して、軽皇子(かるのみこ)を推薦しました。その軽皇子も辞退しましたが、結果、孝徳天皇として即位することとなりました。中大兄皇子は、皇太子となりましたが、孝徳天皇よりも実権を握り続け、孝徳天皇を難波宮に残したまま皇族や臣下の者を引き連れ飛鳥古京に戻ってしまいました。孝徳天皇は失意のまま崩御し、その皇子である有間皇子も謀反の罪で処刑されてしまいました。
中大兄皇子は、天智天皇として即位した後も強引な手法で改革を進めました。皇位継承もそのひとつで、これまでの慣例に代わって唐にならった嫡子相続を目指し、大友皇子への継承を進めました。これらの結果、同母弟である大海人(おおあま)皇子らの不満を高めていきました。当時の皇位継承では、母親の血統や后妃の位も重視されており、身分の低い側室の子の大友皇子の弱点ともなっていました。
これらを背景として大海人皇子の皇位継承を支持する勢力が形成され、強権を誇った天智天皇の崩御とともに、これまでの反動から乱の発生へつながっていったとも考えられています。






