本文
災害時の心得
地震が起こったら・・・
家の中にいるとき
- テーブルなどの下に隠れるなどし、まず安全を確保しましょう。
- あわてて戸外に飛び出さないようにしましょう。
- 出来るだけ早く火を消し、ガスの元栓をしめましょう。
- 火が出たら、速やかに消火しましょう。
- 2階建て以上の家では上階の方が安全です。上階にいたときは、階下に降りないようにしましょう。
- ガラスが落ちているかもしれないので、決して裸足で歩かないようにしましょう。
- 正しい情報をラジオ・テレビなどから入手し、各種警報・注意報に注意し、指示に従い速やかに避難しましょう。

屋外にいるとき
- ブロック塀や電柱など倒壊の危険がある場所からは離れましょう。
- 落下物から頭を守るために、バッグやカバンなどで頭を守りましょう。
- 車の運転中は速やかに安全な場所に停車し、揺れがおさまるまで車外に出ないようにしましょう。
- 車を離れて避難するときは、緊急車両の通行の邪魔にならないようキーはつけたままで、ドアロックしないで、速やかに避難しましょう。その際、検査証など貴重品は忘れずに持ち出すようにしましょう。
- 津波被害が予想される地域では、地震発生と同時にまず海岸から少しでも高台に避難しましょう。

勤め先やお店などにいるとき
- ショーケース、本棚などが転倒するおそれがあるので、できるだけ離れ、座布団やバッグで頭を保護しましょう。
- 避難には階段を使い、慌てずに出口へ向かいましょう。
風水害が起こったら・・・
風水害の危険から身を守るには、日頃から地域の危険箇所を把握しておくことが大切です。
風水害時の心得
- 襲来時期や規模・雨量などは、ある程度予想可能です。梅雨前線や台風シーズンなど、洪水が起こりやすい時期には、テレビ・ラジオ・新聞の天気予報に注意して天気の移り変わりに注意し、必要な場合はすみやかに避難するようにしましょう。
- 危険な土地(造成地・扇状地・山岳地帯・ゼロメートル地帯・海岸地帯・河川敷など)では早めに避難するようにしましょう
- 避難場所までの経路は安全に通行できるか、危険な場所はないか、あらかじめ自分たちで確かめておきましょう。
- 事前に、台風や大雨に備えての周りを点検して、雨戸や雨樋などが痛んでいないか、家の前の排水溝などがつまっていないか確認しましょう。
- 物干し竿や植木鉢などは室内に取り込んでおきましょう。
- 浸水の危険のあるところでは、食料品、衣類、寝具などを上階へ移動しましょう。
- 洪水時に歩ける水深は50~70cmまでです。腰まで水深があるときは無理をせず、高いところで救助を待ちましょう。
避難するときは・・・
災害時は恐怖と不安からパニックが発生する恐れがあるので、正しい情報を入手し、お互いに協力し合い避難するときのルールを守ってください。
安全な避難路の確認を
一時集合場所や避難場所までの経路(避難路)は、あらかじめ自分たちで決めておき、安全に通行できるかを確認しておきましょう。また、一時避難所についても自治会(班・組単位)や自主防災会などであらかじめ決めておきましょう。
正確な情報収集と自主的避難を

ラジオ・テレビで最新の気象情報・災害情報、避難情報に注意しましょう。ガケの近くに住んでいる人は早めに避難しましょう。
避難の呼びかけに注意を

危険が迫ったときには、市役所や消防団から避難の呼びかけをすることがあります。呼びかけがあった場合には、速やかに避難してください。
避難する前に

避難する前に、電気・ガスなどの火元を消し、戸締まりをおこない、避難場所を確認しましょう。また、親戚や知人、隣近所の方などに避難する旨を連絡しておきましょう。
早めの避難を!

身の危険を感じた場合には、自主的判断により早めの避難を心がけましょう。
「避難指示」が出たら・・・
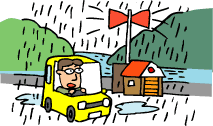
「避難指示」が出たら、ただちに避難しましょう。
危険なところには近づかない

避難場所へ移動するとき、狭い道・塀ぎわ・川べりなどは避ける。
増水した川の様子を見に行くのは大変危険ですので、絶対にやめましょう。
車での移動は控えて

車やバイクでの避難は緊急車両の通行の妨げになります。また、交通渋滞を招き、浸水すると動けなくなりますので、特別な場合を除き徒歩で避難しましょう。
動きやすい格好・2人以上で避難を!

できるだけ1人の行動を避けて、動きやすい服装で避難しましょう。
お年寄りなどの避難に協力を

お年寄りや子供、病気の人などは、早めの避難が必要です。近所のお年寄りなどの避難に協力しましょう。また、日本語が不自由な外国人の避難にも協力しましょう。
安全な避難を
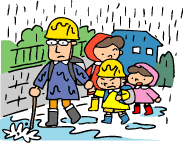
避難路できるだけ高い道路を選び、浸水箇所があった場合は、溝や水路に十分注意し、1m程度の杖か棒の用意を用いて確認しながら歩きましょう。また、ガケ地などでは土砂災害に注意しましょう。
身近な高いところに避難を
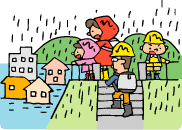
河川増水、河川堤防決壊、津波などで、避難のための十分な時間を確保できない場合や避難所への移動が危険と感じられた場合には、近くの高台や建物の2階以上等の安全な場所に避難しましょう。
非常持出し品の準備をしておきましょう
万が一のときに、すばやく避難できるように、日頃から非常持出し品の準備、定期的に確認しておきましょう。持出品を欲張りすぎると避難時に支障が生じます。およそ10~15kgを目安に公助が本格化するまでの数日間(最低3日分)は自足できるよう非常持出品を確保しておきましょう。
家族構成などを考慮し、必要となる物資の種類・数量を確認しましょう。
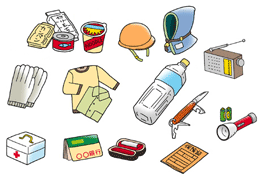
非常持ち出し品
- 携帯ラジオ
- 懐中電灯
- 乾電池
- 貴重品
- 現金
- 預貯金通帳、印鑑
- 免許証
- 権利証書、健康保険証
非常食品
- 乾パン・缶詰
- 栄養補助食品
- ドライフーズ
- ミネラルウォーター
- プラスチックか紙の皿、コップ
- 割り箸
- 缶切り、栓抜き
- 離乳食
- 粉ミルク
- レトルト食品
応急薬品
- ばんそうこう、包帯
- 傷薬、胃腸薬
- 目薬、消毒薬
- 鎮静剤、解熱剤
- 常備薬
その他の生活用品
- 下着・上着・靴下など
- 軍手・タオル
- ティッシュペーパー
- ウェットティッシュ
- 雨具
- ライター
- ビニール袋
- 生理用品、紙おむつ
非常備蓄品
備蓄品は、災害直後から数日間、自足するための物資です。避難したあとで、安全を確認して自宅へ戻り、避難場所へ持ち出したり、自宅で避難生活を送る上で必要なものです。(備蓄食料は1週間以上確保 (PDFファイル:178KB)しましょう。)

非常食品
- 乾パン
- 缶詰やレトルト食品
- アルファ米、レトルトごはん
- ドライフーズ、インスタント食品
- 梅干、チョコレート、飴など
- 栄養補助食品
- 調味料
- 飲料水(ミネラルウォーター)
- その他生活用品
生活用品
- 毛布・寝袋
- 洗面用具
- ポリ容器、バケツ
- なべ、やかん
- 乾電池
- トイレットペーパー
- 使い捨てカイロ
- ろうそく、さらし
- ロープ、バール、スコップ
- ドライシャンプー
- 新聞紙、ビニールシート(燃料、防寒、雨よけ)
- 布製ガムテープ(整理、止血、ガラス補修)
- キッチン用ラップ(止血、汚れた皿に被せる)
- ペットフード
- 自転車
ワンポイント
一人に1個の非常袋を用意する
非常持出品の準備に家族全員が参加すれば、防災意識が高まり、必要なものを入れ忘れることもありません。また、みんなが分担して持てば重量も軽くできます。
非常袋は何カ所かに分散して保管する
家具が倒れたような場合、非常袋が取り出せなかったり、中の物が使えなくなったりするケースも考えられます。庭やベランダなどにも、分散して保管しておきましょう。
車のトランクに非常袋を入れておく
車を運転しているときに地震が起こることもあります。また、家が倒壊したような場合にも、取り出して使える利点があります。
「わが家の防災の日」を決めて中身を点検する。
半年に一回程度、定期的に中身を点検し、期限切れのものは入れ替えましょう。あらかじめ「わが家の防災の日」を決めておくと忘れずにすみます。
近隣の人たちとのコミュニケーションを大切に
避難グループをつくりましょう
地震時の避難の際には、まず集合場所に集まり、人員の点検をしてから避難場所へ移動するため、近隣の人たちと協力することが重要となります。
普段からコミュニケーションをもち、集合場所や集合方法を確認し合いましょう。
要援護者の避難について考えましょう
特に高齢者や障害者の方については、家族だけでは緊急時の対応が難しい場合があります。また、外国人には情報が伝達できないおそれがあります。近隣の人たちと話し合って、救援体制と、分担すべき役割を決めておきましょう。






